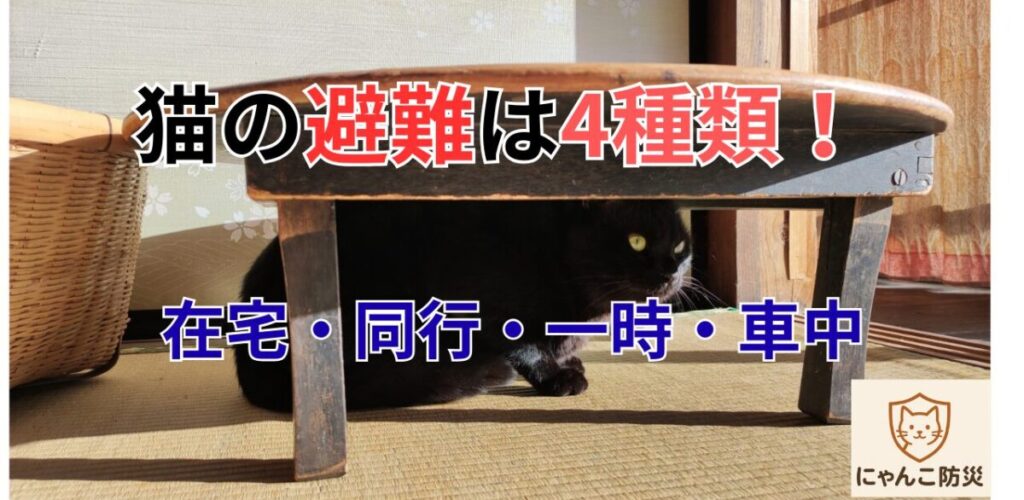
災害のとき、猫の避難先はどこに?
——答えは「在宅・同行・一時・車中」の4択です。
避難先を考える時に大切なのは、家の安全性と猫の負担の2軸で考え、第一候補と第二候補を決めておくことです。
この記事では、猫の避難先の種類を、種類ごとの違いと判断基準、最低限の持ち物チェックリスト、当日あわてないための慣らしトレーニングまで、猫歴40年の実体験を交えてやさしく解説します。
小さな準備が、非常時に猫ちゃんを守れる力に変わります。
猫目線では在宅避難が一番ですが、客観的に家や家族の状況を見て判断しましょう。

猫の避難の種類と違い(在宅・同行・一時・車中)
はじめに: 災害時に迷わないために、避難は大きく「在宅・同行・一時・車中」の4種類に分けて考えると整理しやすいです。
在宅避難:自宅を安全地帯にする
要点: 家が安全なら、猫へのストレスが最も少ない選択です。
自宅の安全性が確保できるなら、停電や断水に備えて「飲水・フード・トイレ資材」を7~10日分キープ。
災害時には猫の脱走件数が跳ね上がりますので、窓・ベランダの脱走対策もしておきましょう。
私は普段から一部屋を「非常時の猫部屋」に決め、ケージ・水・簡易トイレを常備しています。
自宅が「新耐震」か「旧耐震」かを調べるには、建築確認日を知ることが一番確実です。
国土交通省の「住宅・建築物の耐震化について」のページでは、耐震基準の改正年がまとめられています。
👉 住宅・建築物の耐震化について(国交省)
建築日が分からなければ、各自治体の建築課で「建築確認申請日」を証明する書類を取得できます。
同行避難:猫と一緒に避難所へ向かう
要点: 自宅が危険なら、猫と一緒に避難します。
避難所では猫に必要な物資は飼い主が全て準備しなければなりません。

避難所ではケージもしくはキャリーに入れておくことが基本です。
避難所にケージが準備されているかどうか自治体に確認しておきましょう。
同行避難はペットと一緒に避難することで、同伴避難は一緒に避難所に行くことです。
拡張が可能なキャリーなら、避難所でケージの代わりにもなります。
一時退避:親族宅・ホテル・ペットホテルに預ける
要点: 多頭・持病・高ストレスなどで避難所が難しい場合の現実的な解答です。
受け入れ先の候補を事前に決めておき、合意を取っておきましょう。
食事や猫の性格、ワクチン接種記録などのメモを1枚にまとめると引き継ぎがスムーズです。
車中避難:短期の待機・つなぎとして
要点: 開設待ちや一時的退避に限ります。長期は負担が大きいです。
最大のリスクは高温・低温・電力不足。
直射日光を避け、断熱サンシェード・ポータブルファン・水を常備。
トイレは使い捨てトレイ+シートが便利。
やはりネックは夏の暑さです。
ソーラーパネル付きのポータブル電源+小型冷凍庫があれば快適にすごせるはずです。
ポイント早見: どれを選んでも共通のコツは次の3つです。
- まずは在宅>同行>一時>車中の順で検討(家の安全性と猫の負担で判断)
- キャリー慣れと軽量トイレ資材は全パターン共通の準備になります
- 行き先ごとに「猫情報カード」(性格/持病/連絡先)を作っておく
どの避難を選ぶ?判断基準チェック
ポイント: 「家の安全性」と「猫の負担」の2軸で考えると迷いません。
下の4視点を順に見て、第一候補と第二候補を決めましょう。
住まいと地域リスク(地震・水害・土砂)
この視点では、家そのものの安全度を判定します。
- 自宅の強み
- 上階住まい、周囲に危険な建築物なし、家具固定済み、飛散対策あり
- 浸水想定区域外・土砂警戒外、停電時も換気/採光が確保できる
- 自宅の弱み
- 1階で浸水リスク、近くに崖や河川、旧耐震、ガラス多めで飛散が心配、猫の脱走リスク
- 目安
- 強みが多い→在宅避難が第一候補
- 弱みが多い→同行避難や一時退避を第一候補に
家族構成と移動手段(子ども/高齢者/車の有無)
この視点では、移動の負担と現実性を見ます。
- 小さな子・高齢者がいる→近い避難所や親族宅への一時退避が現実的
- 車がある→短時間の車中待機→避難所/親族宅の二段構えが取りやすい
- 車がない→徒歩の同行避難や近所・親族の支援を平時に取り決めて、即行動に移す
猫の性格/健康(キャリー慣れ・持病・老猫)
この視点では、猫の「環境変化に対する強さ」を見ます。
- キャリー慣れ・人混みOK→同行避難の適性高め
- 音や人が苦手・パニック傾向→在宅または親族宅/ホテルへの一時退避
- 投薬中・腎臓/心臓など持病→投薬と水分確保が最優先。静かな一時退避が向く
自治体の受け入れ状況の確認ポイント
この視点では、自治体の受け入れの可否と必要条件を把握します。
政府は同伴避難を推奨していますが、自治体によっては猫の居場所を準備していない所がよくあります。

- ペット受け入れの可否、飼育スペースを確保しているか
- 必携品の指定(ケージ/キャリー、トイレ資材、証明書類)
- 自治会・管理組合ルール(共用部の動線、夜間の鳴き声配慮)
- 平時の連絡先と開設情報の入手方法(掲示板、X、防災メール)
判断早見ヒント:
自宅安全・備蓄あり・環境変化に弱い→在宅。
倒壊/浸水リスク高・キャリー慣れ→同行。
多頭/持病/高ストレス→一時退避。
車中は避難所の開設待ちなどの短期のつなぎに限定。
種類別「最低限の持ち物」チェックリスト
まずは「命・水・トイレ」を優先し、最低限セット→あると安心セットの順で段階的にそろえると続けやすいです。
在宅避難:水・食・トイレ・衛生の備蓄
自宅に留まる場合は、停電・断水に備え「日常を小さく持ち出す」つもりで下記を常備します。
- フード:総合栄養食を7〜10日分以上(普段食の小分け)
- 水:猫用と家族用を分けて確保(ペットボトルを定期ローテ)
- トイレ:軽い紙/木・紙系の砂、シート/ペットシーツ、消臭袋、ミニスコップ
- ケージ/サークル:目隠し用タオルやメッシュカバー
- 衛生:ウェットティッシュ、手袋、ゴミ袋、無香料の消臭アイテム
- 常備薬/処方食:服用方法と量のメモを同封
- 迷子対策:首輪・迷子札、マイクロチップ情報の控え、最新の顔写真
- 情報カード:名前/年齢/性格/持病/投薬/病院連絡先を1枚に
同行避難:キャリー/ケージ/ハーネスは必須
避難所へ移動するときは、安全な移動と周囲への配慮を両立できる装備が基本です。
- キャリー(上開き推奨)or 折りたたみケージ、ハーネス+ダブルリード
- 目隠し用タオル、ブランケット(自宅の匂い付きだと安心)
- フード&水:7〜10日分を小分け、折りたたみ皿、シリンジ/スポイト
- トイレ簡易セット:使い捨てトレイ、ペットシーツ、消臭袋、スコップ
- 証明類:ワクチン記録、診察券、飼い主連絡先、猫の情報カード
- 小物:ライト、モバイルバッテリー(連絡・情報収集用)
一時退避・車中避難:受け入れ先と環境づくり
受け入れ先や車内を一時的な「猫の部屋」にする発想で、すぐ設置できる物を優先します。
- 受け入れ先に渡すもの:猫情報カードのコピー、投薬メモ、食事ルール
- 予備トイレ:使い捨て箱+シーツ(即設置できる状態で)
- 車中の環境:断熱サンシェード、ポータブルファン、温度計
- 暑さ対策:直射日光回避、水の確保、保冷剤はタオルで包む
- 匂い対策:消臭袋、こまめなゴミ回収(長期の車中は負担大、短期のつなぎ)
あると安心:ストレス軽減と小ワザ
必須ではないけれど、猫のストレスを1段下げる「仕上げのひと工夫」です。
- 落ち着く匂いのブランケット/おもちゃ、静かに使える隠れ家
- キャリー拡張パーツ(メッシュ拡張・カバー)
- 予備ハーネス・名札、写真入り迷子チラシのテンプレ
- 口が広い折りたたみボウル、小分けジッパーバッグ、結束バンド
- 使い切りウェットフード(水分補助/食べ慣れたもの)
パッキングのコツ
最初の数時間を滞りなく乗り切るため、使用順にまとめます。
小分け→ジッパーバッグへ1日ぶんセット(フード・シーツ・消臭袋)
袋に日付と中身を書いておく
キャリーの上に「最初に使う袋」を固定。
スムーズに避難するための事前トレーニング
「当日いきなり」は猫にとって負担が大きいので、ふだんの暮らしの延長で少しずつ慣らしておきます。
キャリーに慣らす3ステップ
- 置きっぱなしにして「寝床」にする
・中にお気に入りブランケットやおやつを入れ、出入り自由に。 - 扉を閉める練習を短時間から
・最初は10〜30秒→数分→10分へ。静かな声かけとごほうびを。 - 持ち上げ移動と車/徒歩のプチ体験
・家の中を数歩→玄関→外の空気を少し→短いドライブに拡張。
コツ:上開きタイプは出し入れがラク。目隠しタオルで安心感UP。
トイレ切り替え練習(軽量資材に慣れる)
避難時は「軽い砂+シーツ」が片付けやすいので、事前に慣れさせます。
・普段の砂:新砂=7:3→5:5→3:7と1〜2週間かけて移行。
・使い捨てトレイを時々使い、本番の手順(敷く→捨てる)を飼い主も練習。
名前呼び・呼び戻し
・短い合図(例:「おいで」)を決め、来たら即ごほうび。
・家の別室や玄関周りでも成功体験を積み、反応の精度を上げる。
・首輪+迷子札は常用にし、マイクロチップ情報を最新に。
ハーネス/リード装着の慣らし
・室内で数分から装着→遊びとごほうびで「良いこと」と結びつける。
・装着中に歩く→抱っこ→キャリー出入りまで小刻みに練習。
・本番はダブルリードで脱走リスクを二重に抑える。
鳴きやすい/怖がりさんへの配慮
・匂いのついた毛布で「自分の匂いの空間」を持ち歩く。
・目隠しで視覚刺激を減らす。移動中の声かけは低くゆっくり。
・短時間の練習を毎日1回のペースで継続(長時間は逆効果)。
ミニ課題:
「週1回・10分の避難ごっこ(キャリーIN→玄関→外気吸う→帰宅)」を家族でルーティン化しておくと、本番に強くなります。
よくある不安とマナーQ&A
避難時は「周囲への配慮」と「猫の安心」の両立がポイント。よくある不安に、実践しやすい小ワザで答えます。
鳴き声・ニオイ対策は?
静かに過ごせる環境づくりと、においの即時リセットでトラブルを防ぎます。
- 目隠しタオル+自宅の匂いが付いたブランケットで落ち着かせる
- 移動前にトイレを済ませ、排泄はすぐ密閉(消臭袋を二重)
- 水分多めのウェットで満腹感をサポート/静音ファンで暑さ軽減
- 近隣へひと言あいさつ(「猫連れです。音が大きければ教えてください」)
ケージは狭くて可哀想?
短期の「安全地帯」と割り切り、レイアウトとケアで負担を下げます。
- 寝る・食べる・排泄を三角配置/上半分を覆って視覚刺激を減らす
- 1日数回のケアタイム(撫でる・水替え・トイレ清掃)
- こぼれにくい浅皿+重し/給水は浅めの器やノズル型も検討
多頭飼いの分け方・順番は?
確保の順序と資材の数でケンカと混乱を防ぎます。
- 相性の悪い組は別キャリー
- トイレは頭数+1、食器も個別に
- 投薬・持病のある子を先に確保/カラー別の情報カードで識別
避難所での配慮(場所・時間・清掃)
施設ルールに沿って、できるだけ静かに清潔に。
- ペットゾーンを使用/通路移動は抱っこ or キャリーのみ
- 清掃は自前でこまめに(除菌ウェット・消臭袋を常備)
- 夜は早めにカバーで消灯モード/ゴミ出しルール厳守
脱走が怖い
開閉の所作と装備で“二重ロック”を。
- ダブルリード+ハーネス(指1本入るフィット感)
- キャリー開閉は可能なら二人作業
- 迷子チラシのテンプレと写真(正面/横)をスマホと紙で用意
持病猫・老猫の体調管理
日課の継続と温度管理が要。
- 薬は日付ごと小分け
- 体温調整:カイロ/保冷剤はタオル越しで直肌NG
- 食事量・尿便・呼吸のチェック表で早めに変化に気づく
手伝ってくれる人へのお願いの仕方
「何を・いつ・どれだけ」を具体化します。
- 例:「この袋が1日分です」「10時に1/4錠をフードに混ぜて」
- 情報カードに連絡先QRと既往歴を記載/お礼の一言を忘れずに
まとめ
避難は「在宅・同行・一時・車中」の4種類。
まずは家の安全性と猫の負担で第一候補+第二候補を決め、平時に家族で共有すれば迷いません。
最低限は水・フード・トイレ、そしてキャリー/ハーネス。
情報カードと顔写真、投薬メモも1枚にまとめておくと移動先で助かります。
今日できるのは、
①キャリーを出しっぱなしにして慣らす
②備蓄をチェックする
③自治体の受け入れ条件を確認。
軽い砂・消臭袋・折りたたみケージのような“軽くて片付けやすい道具”は、猫のストレスを下げ、あなたの手間も減らします。
小さな一歩を今はじめれば、非常時にも愛猫をしっかり守れます。
